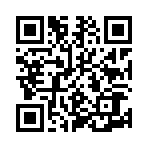諏訪地域 諸データ
諏訪地域火の見櫓 発見総数 370(内撤去済 17)
諏訪地域の火の見櫓を語るうえで、重要なのは、なんといっても、梯子型と一本足の数が
他地域にくらべて圧倒的に多いことである。
四脚ないし三脚櫓をメインにおいて、スキマに梯子型or一本足を配置しているようだ。
隣の山梨県にも梯子型が多いので、地続きでその影響によるのかもしれない。
また、梯子型の形がほぼ共通している点も興味深い。
屯所建替えに際して、櫓はそのまま残されることが多いが、建替えて三脚or四脚の
ホース乾燥塔に入れ替わることもあるようだ。
他地域では隣接する建物とともに撤去されるのに、わざわざ残そうとする姿勢は
ありがたいが、そのへんの方針の違いはどこからくるのだろうか?
●脚の数
割合としては、やはりオーソドックスな櫓四脚型がいちばん多い。
三脚は、10%くらいで、少なめである。
近年になって建て替えると、四角柱四脚型に変わってしまうようで、よそより少々多め。




櫓四脚 193 梯子型 91 三脚 31 一本 31



四角柱四脚 12 三角柱 10 二脚 1
●屋根飾り
銘板トップ数の坂本鉄工所を中心に、ほとんどが避雷針である。
風向計は、中村ポンプ工場など他の鉄工所製にみられるようだった。



避雷針 157 風向計 71 方位針 3
●屋根の形
これも、四角は坂本鉄工所、六角は中村ポンプ工場と、よくみられる鉄工所製で形が分かれた。
三角には、乙事の梯子型も含まれている。



四角 176 六角 35 三角 11


丸 6 八角 1
●見張り台(上)の形



八角 109 四角 64 丸 42



三角 21 六角 7 十二角 4
●踊り場の形



四角 151 丸 12 八角 9

三角 5
●銘板にみる鉄工所名
銘板にみる鉄工所名では、ダントツで坂本鉄工所が多かった。岡谷をのぞく全市町村をカバー
しているが、やはり地元富士見から茅野までが特に数がある。
次いで、山梨から中村ポンプ工場。こちらも富士見から茅野までが守備範囲のようである。
その他、地元鉄工所中心に製作されている中、加茂川鉄工所のみ東京である。



坂本鉄工所 51 中村ポンプ工場 21 諏訪市 宏和鐵工所 8



長田鉄工所 3 岡谷市 小原鉄工所 3 中村鉄工所 2



伊那松島 赤羽商会 2 大久保鉄工所 2 中村ポンプ詰機械工作所? 2



藤原鉄工場製? 1 原鐡工所 1 加茂川鉄工所 1



岡谷造機株式会社 1 岡谷銅鉄株式会社 1 窪田鉄工所 1
●半鐘の存在
ほとんどの櫓に半鐘があり、上・見張り台と下・踊り場付近or足元と両方ある場合も多かった。
▽上の半鐘
総数 334

銅製の古いもの 95

鉄製で表面に凹凸のない簡易なもの 239
▽下の半鐘
総数 136

銅製の古いもの 45

鉄製で表面に凹凸のない簡易なもの 91
▽上下両方ある場合
上下とも銅製 9
上下とも鉄製 54
上:銅製 下:鉄製 19
上:鉄製 下:銅製 29
上:銅製 下:銅製&鉄製 1
●信号表の存在
信号表残存率が、よその地域にくらべて高めである。
ほとんどの櫓に信号表があり、梯子型であっても備え付けられている。
原村では多くの信号表が、地震信号付の新しいものになっていて、古いものはあまりなかった。
総数 112


警鐘信號 3 横長 1
旧字体


太 23 細 42
新字体


太 9 細 6
地震信号付


白地 17 サビ 2
●梯子の付き方
まず、踊り場の有無によっても、付き方が異なる。
大きく分けて、以下の4種になる。
a 踊り場のない、外梯子のみのもの
b 踊り場のない、内梯子のみのもの
c 踊り場まで外梯子、見張り台まで内梯子
d 踊り場まで内梯子、見張り台まで内梯子
▽三脚
三脚櫓では、外梯子のみのタイプが一番多かった。比較的細身になるからだろうか。
内梯子のみタイプは富士見だけでみられた。
外梯子→内梯子タイプは、茅野の塚原の、中村鉄工所製2基だけである。


a 外梯子のみ 25 b 内梯子のみ 2

c 外梯子→内梯子 2
○三角柱
三角柱タイプでは、外梯子のみしか見られなかった。

a 外梯子のみ 10
▽四脚
四脚櫓では、踊り場を入れた外梯子→内梯子タイプが、半分以上を占めている。
細身からかなり幅広のものまで、このタイプはバリエーションが多い。
内梯子→内梯子タイプは、中村ポンプ工場製によくみられる。
外梯子or内梯子のみタイプは、比較的小型のもののみのようである。


a 外梯子のみ 3 b 内梯子のみ 5


c 外梯子→内梯子 127 d 内梯子→内梯子 57
○四角柱
意外と種類があった四角柱。
外梯子→内梯子というか、詰所の階段からそのままのぼるタイプ。
だいたい四角柱は幅広ででかいものが多いので、内梯子のみが多いのは、スペースに余裕が
あり、あえて外梯子を必要としないからだろう。


b 内梯子のみ 1 c 外梯子→内梯子 4

d 内梯子→内梯子 7
●設置年代
銘板、地区誌等から判明した設置年代は以下のグラフのようになっている。
戦後、昭和29年から30年代にかけて、多く製作されたようだ。
諏訪地域の火の見櫓を語るうえで、重要なのは、なんといっても、梯子型と一本足の数が
他地域にくらべて圧倒的に多いことである。
四脚ないし三脚櫓をメインにおいて、スキマに梯子型or一本足を配置しているようだ。
隣の山梨県にも梯子型が多いので、地続きでその影響によるのかもしれない。
また、梯子型の形がほぼ共通している点も興味深い。
屯所建替えに際して、櫓はそのまま残されることが多いが、建替えて三脚or四脚の
ホース乾燥塔に入れ替わることもあるようだ。
他地域では隣接する建物とともに撤去されるのに、わざわざ残そうとする姿勢は
ありがたいが、そのへんの方針の違いはどこからくるのだろうか?
●脚の数
割合としては、やはりオーソドックスな櫓四脚型がいちばん多い。
三脚は、10%くらいで、少なめである。
近年になって建て替えると、四角柱四脚型に変わってしまうようで、よそより少々多め。




櫓四脚 193 梯子型 91 三脚 31 一本 31



四角柱四脚 12 三角柱 10 二脚 1
●屋根飾り
銘板トップ数の坂本鉄工所を中心に、ほとんどが避雷針である。
風向計は、中村ポンプ工場など他の鉄工所製にみられるようだった。



避雷針 157 風向計 71 方位針 3
●屋根の形
これも、四角は坂本鉄工所、六角は中村ポンプ工場と、よくみられる鉄工所製で形が分かれた。
三角には、乙事の梯子型も含まれている。



四角 176 六角 35 三角 11


丸 6 八角 1
●見張り台(上)の形



八角 109 四角 64 丸 42



三角 21 六角 7 十二角 4
●踊り場の形



四角 151 丸 12 八角 9

三角 5
●銘板にみる鉄工所名
銘板にみる鉄工所名では、ダントツで坂本鉄工所が多かった。岡谷をのぞく全市町村をカバー
しているが、やはり地元富士見から茅野までが特に数がある。
次いで、山梨から中村ポンプ工場。こちらも富士見から茅野までが守備範囲のようである。
その他、地元鉄工所中心に製作されている中、加茂川鉄工所のみ東京である。



坂本鉄工所 51 中村ポンプ工場 21 諏訪市 宏和鐵工所 8



長田鉄工所 3 岡谷市 小原鉄工所 3 中村鉄工所 2



伊那松島 赤羽商会 2 大久保鉄工所 2 中村ポンプ詰機械工作所? 2



藤原鉄工場製? 1 原鐡工所 1 加茂川鉄工所 1



岡谷造機株式会社 1 岡谷銅鉄株式会社 1 窪田鉄工所 1
●半鐘の存在
ほとんどの櫓に半鐘があり、上・見張り台と下・踊り場付近or足元と両方ある場合も多かった。
▽上の半鐘
総数 334

銅製の古いもの 95

鉄製で表面に凹凸のない簡易なもの 239
▽下の半鐘
総数 136

銅製の古いもの 45

鉄製で表面に凹凸のない簡易なもの 91
▽上下両方ある場合
上下とも銅製 9
上下とも鉄製 54
上:銅製 下:鉄製 19
上:鉄製 下:銅製 29
上:銅製 下:銅製&鉄製 1
●信号表の存在
信号表残存率が、よその地域にくらべて高めである。
ほとんどの櫓に信号表があり、梯子型であっても備え付けられている。
原村では多くの信号表が、地震信号付の新しいものになっていて、古いものはあまりなかった。
総数 112


警鐘信號 3 横長 1
旧字体


太 23 細 42
新字体


太 9 細 6
地震信号付


白地 17 サビ 2
●梯子の付き方
まず、踊り場の有無によっても、付き方が異なる。
大きく分けて、以下の4種になる。
a 踊り場のない、外梯子のみのもの
b 踊り場のない、内梯子のみのもの
c 踊り場まで外梯子、見張り台まで内梯子
d 踊り場まで内梯子、見張り台まで内梯子
▽三脚
三脚櫓では、外梯子のみのタイプが一番多かった。比較的細身になるからだろうか。
内梯子のみタイプは富士見だけでみられた。
外梯子→内梯子タイプは、茅野の塚原の、中村鉄工所製2基だけである。


a 外梯子のみ 25 b 内梯子のみ 2

c 外梯子→内梯子 2
○三角柱
三角柱タイプでは、外梯子のみしか見られなかった。

a 外梯子のみ 10
▽四脚
四脚櫓では、踊り場を入れた外梯子→内梯子タイプが、半分以上を占めている。
細身からかなり幅広のものまで、このタイプはバリエーションが多い。
内梯子→内梯子タイプは、中村ポンプ工場製によくみられる。
外梯子or内梯子のみタイプは、比較的小型のもののみのようである。


a 外梯子のみ 3 b 内梯子のみ 5


c 外梯子→内梯子 127 d 内梯子→内梯子 57
○四角柱
意外と種類があった四角柱。
外梯子→内梯子というか、詰所の階段からそのままのぼるタイプ。
だいたい四角柱は幅広ででかいものが多いので、内梯子のみが多いのは、スペースに余裕が
あり、あえて外梯子を必要としないからだろう。


b 内梯子のみ 1 c 外梯子→内梯子 4

d 内梯子→内梯子 7
●設置年代
銘板、地区誌等から判明した設置年代は以下のグラフのようになっている。
戦後、昭和29年から30年代にかけて、多く製作されたようだ。
| 年代別設置数 | ||
| 大正15年: | 1 | |
| 昭和21年: | 1 | |
| 昭和26年: | 1 | |
| 昭和27年: | 1 | |
| 昭和28年: | 1 | |
| 昭和29年: | 8 | |
| 昭和30年: | 8 | |
| 昭和31年: | 6 | |
| 昭和32年: | 2 | |
| 昭和33年: | 13 | |
| 昭和34年: | 6 | |
| 昭和35年: | 5 | |
| 昭和36年: | 15 | |
| 昭和37年: | 6 | |
| 昭和38年: | 10 | |
| 昭和39年: | 6 | |
| 昭和40年: | 2 | |
| 昭和43年: | 1 | |
| 昭和44年: | 2 | |
| 昭和48年: | 2 | |
| 昭和52年: | 1 | |
| 昭和58年: | 1 | |
| 平成: | 4 |
Posted by 某タヌキ at
◆2009年03月01日21:04
│雑感