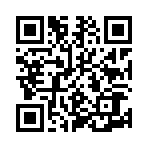考察その5 欄干 上
過去記事は、実はいろいろ増えてるのだけど、日付としては古いのでわかりにくいという。
場所ごとに合わせておきたいもんで、カテゴリで一括にできるとはいえ、新記事にはしにくい。
ここんところは、図書館で地域誌をあさって櫓に関する記事を、いろいろピックアップ中。
ものすごーく細かくのってるとこもあれば、さっぱりのってねえ!ってとこもある。
あと、知りたい肝心な情報がない!ってのもあって、がっくり。ああ。
それから、銘板と記述で日付がちがうのはどういうことなんだ?
誤植はともかく、尺貫法を単位ただmに直すだけってありえないだろ、というツッコミはある。
とはいえ、先人たちがこうしてまとめてくれてあるので、後でこうして探すのもある程度楽になってる
はず。ありがたいことです。
読んでて、戦中供出に出されたものが多かったのと、大正あたりに作られた鉄骨櫓は、なーんか
やたらここらでいちばんでかかった!みたいな主張が多かったのが、気になった。
こんな山中で、戦前でも、結構技術が進んでたのか。
まとめられそうだったら、そのうち記事に。個々の記事に付け加えるかもしれないけど。
今回は見張り台の欄干装飾について。とりあえず、上から。
△三角型

見張り台自体がごく狭く、装飾は特にない。
下部にふくらみがあるくらいである。


これも装飾はない。
三角形の一辺にホース乾燥フック、
別の一辺から出入りできるようになって
いる。

櫓本体の筋交いと同じXと○。
入口部分が丸くふくらんでいる。
上のものにくらべて、かわいらしい感じ。
十二角型

ほぼ円に近い十二角。
格子状で、装飾はなし。
梯子出入口のみ開いている。
このタイプは外梯子のみである。
下諏訪にみられる。



六角型

三角にもあった筋交いXと○。
ホース乾燥フックがついている。
左のタイプは内梯子だが、外梯子タイプだと
六角の一辺が出入口になり、三角同様
丸くふくらむ。
このタイプは富士見にみられる。



六角の一辺が出入口として、
丸くふくらんでいる。
多少大きさにばらつきはあるが、
基本的に丸と逆ハート型のような模様で
ある。



○丸型

装飾なし、柵のみ。
ホース乾燥フック付。
床板?の形で三脚か四脚かがわかる。



筋交いXと○。
ホース乾燥フックは、柵ではなく
別にはみ出して付けられている。
このタイプは岡谷にみられる。



六角にもあった丸と逆ハート模様。
ホース干しは柵にじかについている。
中村ポンプ工場製はこのタイプである。
その他のものには、下の逆ハートが
上の柵と離れているものもある。
六角屋根が多い。
































逆ハート型のみで、上の丸なし。
このへん唯一の八角屋根で、
各部のデザインも微妙に違うのかも。
柵上部外側にふちがついてる。
□四角型

装飾のない、縦柵のみ。
上下分かれてるものもあり。




縦横交差させたカゴみたいなタイプ。
ホース乾燥フックは一辺に付いている。



○のない筋交いのXのみの柵。


三角・六角・丸型同様の筋交いXと○。
大きさは様々で、一辺にXと○のパターンが
2つから最多で6つまである。
諏訪と岡谷にみられる。
▼2つ



▼3つ



長方形タイプ 2つ×3つ




▼4つ







▼5つ ▼6つ



上下が開いていて、真ん中に装飾。
ひげが長めで隣同士くっついているので、
ハート型にも逆ハート型にもみえる。


逆ハート型。
パターンの間上部に3を横にしたような
ひげ飾りがある。

○と逆ハート型。
一辺に○ふたつと逆ハートのパターンが
5つのものと6つのものがある。
富士見に多い。
▼5つ






▼6つ





八角型

装飾なし、縦柵のみ。
上部にホース干し用ふちが広がった
タイプもみられる。
宏和鉄工所製がこのタイプ。






横枠がひとつだけ付いている。
縦だけの中、いいアクセントになっている。

ハート型のひげ飾りが、控えめにふたつ
だけ付いている。

筋交いXと○タイプ。
八角の四隅部分はパターンひとつだが、
辺部分では、パターンが四角同様、
2つ~5つまで幅がある。
これも諏訪と岡谷にみられる。





上部にX字が増えている。
外側にふちがついている。

こちらは逆に、下部に縦柵。

横並び亀甲模様、上下にひげ。
上伊那によくみられる模様。
辰野町寄りの場所にみられるので、
諏訪圏より上伊那の影響があるのだろう。



上部にX字、下部に逆ハート型。
これも上伊那にみられる模様。
上同様、上伊那寄りの影響だろう。


上と模様の構造は同じだが、上下の
パターンの位置が違う。
上伊那系では、上下パターンにズレがあるが、
これは一緒になっている。

上のひげ同士がくっついてハート型に
みえる。

逆ハート型で、上のひげまでの間が
長い。


上下のひげの丸まり方が同じくらいで
ちょっとはさみっぽい感じ。

○と逆ハート型。
いちばん数が多い。
坂本鉄工所製がこのタイプ。
四角同様、一辺におけるパターン数に
3、4、4・5と種類がある。
▼4つで、上下に隙間のあるもの












逆ハート型のパターンが半分ずつずれ
て、四隅の角にかぶっている。
長田鉄工所製がこのタイプ。


▼4.5で上下に隙間があるもの

一辺にパターン4つ+半分。


▼4つで、下に隙間のあるもの






▼4つで、上下とも隙間なし


▼3つで、上に隙間のあるもの

▼4つで、上に隙間のあるもの


















































●総括
見張り台の形は様々でも、欄干の模様はほぼ共通している。
また、市ごとでも特色があるのがわかる。
筋交いX字と○のパターンは、岡谷、諏訪に多くみられ、○と逆ハートのパターンは富士見~茅野に
多い。下諏訪は、わりと櫓ごとにばらつきがある。
鉄工所ごとなどで、同じ模様であってもパターンの仕方が異なるのも興味深い。
場所ごとに合わせておきたいもんで、カテゴリで一括にできるとはいえ、新記事にはしにくい。
ここんところは、図書館で地域誌をあさって櫓に関する記事を、いろいろピックアップ中。
ものすごーく細かくのってるとこもあれば、さっぱりのってねえ!ってとこもある。
あと、知りたい肝心な情報がない!ってのもあって、がっくり。ああ。
それから、銘板と記述で日付がちがうのはどういうことなんだ?
誤植はともかく、尺貫法を単位ただmに直すだけってありえないだろ、というツッコミはある。
とはいえ、先人たちがこうしてまとめてくれてあるので、後でこうして探すのもある程度楽になってる
はず。ありがたいことです。
読んでて、戦中供出に出されたものが多かったのと、大正あたりに作られた鉄骨櫓は、なーんか
やたらここらでいちばんでかかった!みたいな主張が多かったのが、気になった。
こんな山中で、戦前でも、結構技術が進んでたのか。
まとめられそうだったら、そのうち記事に。個々の記事に付け加えるかもしれないけど。
今回は見張り台の欄干装飾について。とりあえず、上から。
△三角型

見張り台自体がごく狭く、装飾は特にない。
下部にふくらみがあるくらいである。


これも装飾はない。
三角形の一辺にホース乾燥フック、
別の一辺から出入りできるようになって
いる。

櫓本体の筋交いと同じXと○。
入口部分が丸くふくらんでいる。
上のものにくらべて、かわいらしい感じ。
十二角型

ほぼ円に近い十二角。
格子状で、装飾はなし。
梯子出入口のみ開いている。
このタイプは外梯子のみである。
下諏訪にみられる。



六角型

三角にもあった筋交いXと○。
ホース乾燥フックがついている。
左のタイプは内梯子だが、外梯子タイプだと
六角の一辺が出入口になり、三角同様
丸くふくらむ。
このタイプは富士見にみられる。



六角の一辺が出入口として、
丸くふくらんでいる。
多少大きさにばらつきはあるが、
基本的に丸と逆ハート型のような模様で
ある。



○丸型

装飾なし、柵のみ。
ホース乾燥フック付。
床板?の形で三脚か四脚かがわかる。



筋交いXと○。
ホース乾燥フックは、柵ではなく
別にはみ出して付けられている。
このタイプは岡谷にみられる。



六角にもあった丸と逆ハート模様。
ホース干しは柵にじかについている。
中村ポンプ工場製はこのタイプである。
その他のものには、下の逆ハートが
上の柵と離れているものもある。
六角屋根が多い。
































逆ハート型のみで、上の丸なし。
このへん唯一の八角屋根で、
各部のデザインも微妙に違うのかも。
柵上部外側にふちがついてる。
□四角型

装飾のない、縦柵のみ。
上下分かれてるものもあり。




縦横交差させたカゴみたいなタイプ。
ホース乾燥フックは一辺に付いている。



○のない筋交いのXのみの柵。


三角・六角・丸型同様の筋交いXと○。
大きさは様々で、一辺にXと○のパターンが
2つから最多で6つまである。
諏訪と岡谷にみられる。
▼2つ



▼3つ



長方形タイプ 2つ×3つ




▼4つ







▼5つ ▼6つ



上下が開いていて、真ん中に装飾。
ひげが長めで隣同士くっついているので、
ハート型にも逆ハート型にもみえる。


逆ハート型。
パターンの間上部に3を横にしたような
ひげ飾りがある。

○と逆ハート型。
一辺に○ふたつと逆ハートのパターンが
5つのものと6つのものがある。
富士見に多い。
▼5つ






▼6つ





八角型

装飾なし、縦柵のみ。
上部にホース干し用ふちが広がった
タイプもみられる。
宏和鉄工所製がこのタイプ。






横枠がひとつだけ付いている。
縦だけの中、いいアクセントになっている。

ハート型のひげ飾りが、控えめにふたつ
だけ付いている。

筋交いXと○タイプ。
八角の四隅部分はパターンひとつだが、
辺部分では、パターンが四角同様、
2つ~5つまで幅がある。
これも諏訪と岡谷にみられる。





上部にX字が増えている。
外側にふちがついている。

こちらは逆に、下部に縦柵。

横並び亀甲模様、上下にひげ。
上伊那によくみられる模様。
辰野町寄りの場所にみられるので、
諏訪圏より上伊那の影響があるのだろう。



上部にX字、下部に逆ハート型。
これも上伊那にみられる模様。
上同様、上伊那寄りの影響だろう。


上と模様の構造は同じだが、上下の
パターンの位置が違う。
上伊那系では、上下パターンにズレがあるが、
これは一緒になっている。

上のひげ同士がくっついてハート型に
みえる。

逆ハート型で、上のひげまでの間が
長い。


上下のひげの丸まり方が同じくらいで
ちょっとはさみっぽい感じ。

○と逆ハート型。
いちばん数が多い。
坂本鉄工所製がこのタイプ。
四角同様、一辺におけるパターン数に
3、4、4・5と種類がある。
▼4つで、上下に隙間のあるもの












逆ハート型のパターンが半分ずつずれ
て、四隅の角にかぶっている。
長田鉄工所製がこのタイプ。


▼4.5で上下に隙間があるもの

一辺にパターン4つ+半分。


▼4つで、下に隙間のあるもの






▼4つで、上下とも隙間なし


▼3つで、上に隙間のあるもの

▼4つで、上に隙間のあるもの


















































●総括
見張り台の形は様々でも、欄干の模様はほぼ共通している。
また、市ごとでも特色があるのがわかる。
筋交いX字と○のパターンは、岡谷、諏訪に多くみられ、○と逆ハートのパターンは富士見~茅野に
多い。下諏訪は、わりと櫓ごとにばらつきがある。
鉄工所ごとなどで、同じ模様であってもパターンの仕方が異なるのも興味深い。
Posted by 某タヌキ at
◆2009年02月23日17:29
│雑感